ご利用ガイド一覧はこちら
-
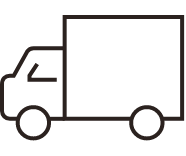
配送・送料について
ご注文商品は、受付後4日前後でお届けとなります(地域と発送事情により、多少遅れる場合もございます)。
1回のご注文が5,000円以上、または定期コースのご利用で送料無料となります。5,000円(税込)未満の場合は送料500円(税込)がかかります。 -
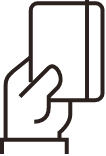
お支払い方法について
お支払い方法はクレジットカード、後払い振込(郵便局・コンビニエンスストア・スマートフォン決済)、代金引換の3種類からお選びいただけます。
-
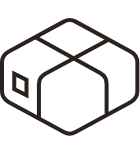
返品について
商品到着日より8日以内は商品の返品が可能です(商品開封後不可)。
アリナミン製薬ダイレクトお客様係(0120-866-333)までお電話ください。 -
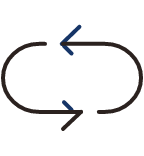
定期コースについて
お客様のご使用周期に合わせて、自動的に送料無料でお届けします。
毎回、通常価格の10%OFFになるなどお得な特典を受けられますので、ぜひご利用ください。 -
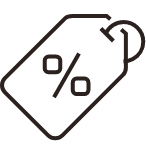
まとめ買い割引について
まとめて商品をご購入いただくと5%~10%割引となります。
-
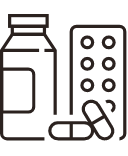
医薬品のご購入について
医薬品のご購入に関する店舗情報や販売制度に関するご案内です。


 メニュー
メニュー 医薬品
医薬品







 健康補助食品
健康補助食品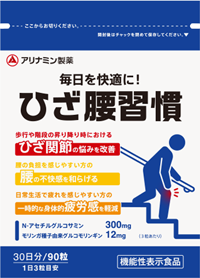




 ヘアケア
ヘアケア


 入浴剤
入浴剤


 CLOSE
CLOSE

